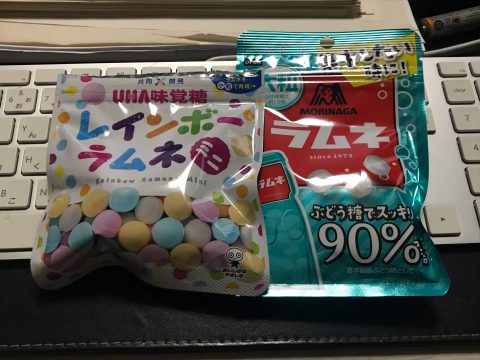4月8日頃にガチャンと切り替える予定
2022年4月6日(水)の午前中に,ガチャンと切り替えようかと思いましたが,肝心なBIND (named)の設定がまだと気がつき,着手しましたが,難航しています.
もともとBINDのことはあんまり理解してないまま使ってきてました.解ってないのにいろいろ過去の複雑な事情が設定に盛りこまれています.
BINDもセキュリティーの事情からバージョンが上がる度にそういう曖昧さが許されなくなってきているようで,Slackware 14.xで動いていた設定をそのままコピーしても,エラーが出て動いてくれませんでした.
ということで,1, 2日かけて,BINDの設定をチューニングしてから,いよいよガチャンと切り替えます.
追記: とりあえずBIND動きました
BIND (named)の設定のエラーは,メッセージを見ながら,理解していないなりに😓 直して,エラーが出なくなりました.
しかし,システムを起動しても,namedもntpdも動いていない.前のシステムの起動手順などを見てみても,特に変わらないのですが.
なんとなく勘で,システムの時間が設定されていないとnamedが動かず,namedが動いていないから,ntpdがサーバーのipアドレスを取得できなくて動かないのではないか,と当たりを付けました.
一番の問題は,Raspberry Pi Model Bシリーズが,バッテリーにより駆動されるhardware clockを持っていないことです.起動時に何もしないと,1970年1月1日から始まってしまいます.
もともとの起動順は,rc.Mから呼ばれたrc.inet2によって,rc.bindがスタートして,そのあと,rc.Mの少し後でrc.ntpdが起動されます.これでしばらくするとclockが同期しますが,少し時間がかかるので,ntpd起動の前に,
/usr/sbin/ntpdate 0.pool.ntp.org
を実行するように,rc.ntpdに追加してあります.
SlackwareARM 14.xではこれで問題ありませんでした.つまり,システムの時間が1970年1月1日でもnamedは起動して,その後に起動するntpdのサーバー名を解決してくれます.しかし,SlackwareARM 15.0付属のBIND 9.16.xでは,システムの時間がめちゃくちゃだと,namedが居座らずに異常終了してしまいます.
そして,ntpdが時間サーバーのipアドレスを解決できずにやはり異常終了してしまう.
「ニワトリが先かたまごが先か」問題です.
仕方がないので,0.pool.ntp.orgでたまたま表示される1つのipアドレス(仮にnn.nn.nn.nn)を使い,rc.Mの中のrc.inet2起動の前に,
/usr/sbin/ntpdate nn.nn.nn.nn
を書いて,解決しました.poolなのに,固定的に使うのは趣旨に反すると思いますが,起動時の一回だけだから勘弁しもらいましょう.