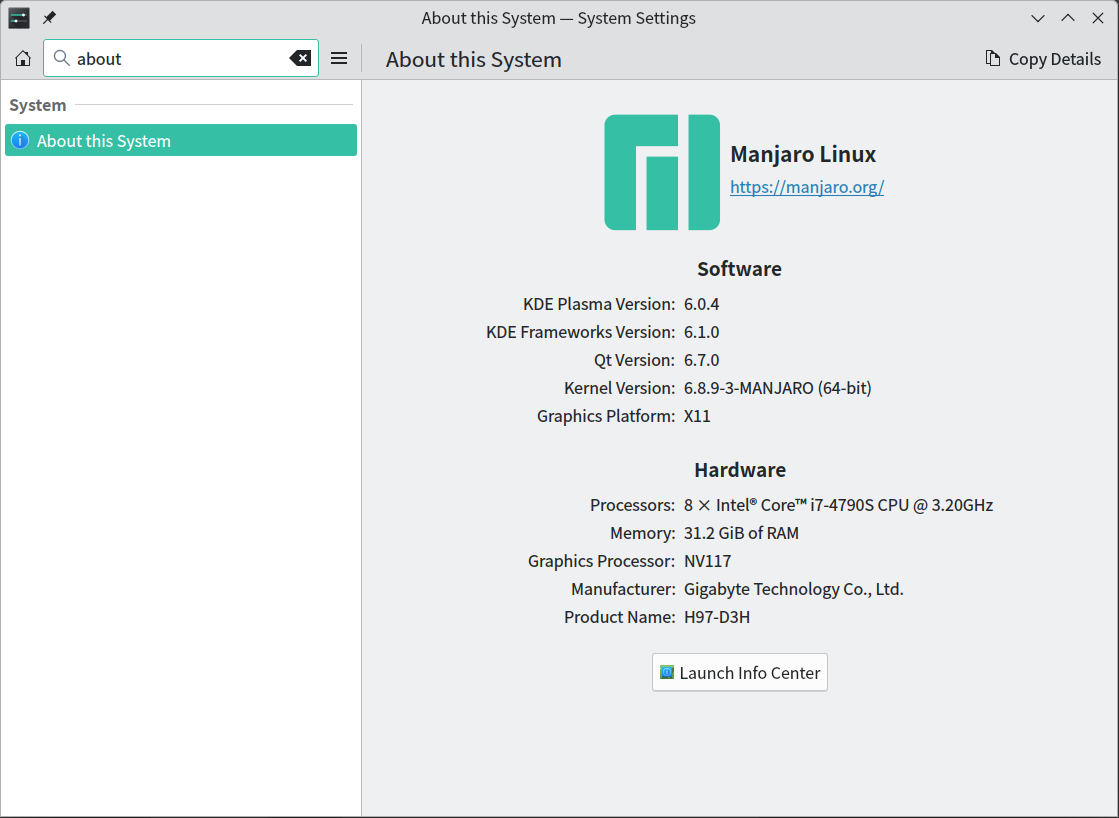ある程度確率・統計を学び,世の中は因果律に支配されていることを念頭に生きて,日頃の国内外の政治,経済などのニュースもある程度追いかけていれば,「投資はギャンブルだ」ということが自然と結論として出てきます.
ところがどっこい.「投資はギャンブル」でネット検索すると,「投資はギャンブルではない」という記事がずらりとヒットします.投資はギャンブルではない原理主義の宗教が蔓延しているかのようです.
バカバカしいけどいくつかの記事を斜め読みしたところ.
- 投資とギャンブルは元本保証でなく最終的に “自己責任” (という本質)は同じ
- 社会貢献している将来有望な会社への投資は間接的な社会貢献
なんてことが書かれています.そう,本質は同じなんです.また2番目は重大問題ですね.競馬,競輪,競艇,オートレースファンは馬の魅力や騎手や選手たちの人柄や将来性に賭ける人も少なくないです.そうした公営ギャンブルファンを敵に回しています.
こんなことまででっち上げないと差別化ができないということなのでしょう.
逆に民間企業がうちは社会貢献しています,人材育成していますと自称したところでその裏まで取って投資している人はどれだけいるんでしょうか.
FXやバイナリーオプションに至っては,誰が見ても危険なギャンブルです.
また,一番納得いかないのは巨大地震など大規模災害に対する投資のリスクを「ないよ教」のサイトが詳しく説明していないところです.AI投資などはある程度は加味していると思いますが,それでもリスクを科学的に言われている水準まで上げるとリスクが勝ってどこにも投資できなくなると思います.
投資はギャンブルだと割り切って無理なく投資する(=賭ける)のが大事だと思います.
ギャンブルは期待値1未満
そうは言ってももともと売上から胴元(公営ギャンブル主催者)の取り分を取ってから払戻金を分配する公営ギャンブルに対して,投資は得した人損した人を平均すれば元本+αになる可能性が高いので別物でしょう,って筆者もずっと考えていました.その考えを変えたのが,この最高裁判決です.
外れ馬券が必要経費に当たるという判断は常識的に考えれば当たり前の話で,特に画期的とは思いませんが,関連のニュースでこの被告は自作のソフトで馬券を購入して経常的に利益を得ていたということを知って驚きました.
以後競馬は投資の対象になり得ると確信していますし,似たような投票システムの公営ギャンブルには皆その可能性があると思います.
一方で投資にもFXのようにギャンブル性が高いものもあります,というかそれこそギャンブルそのものです😅
また期待値が1未満かどうかがギャンブルと投資の違いとすると,長らく低迷していた日本の株,外貨や暗号資産など,短期・中期的には期待値が1にならない状態が多々あります.
投資の経験則
- 金持ちは投資で儲けるが貧乏人は投資しても大して儲からないか損をする
- 金持ちは大損したら補填されるが貧乏人は全部自己責任
少なくとも投資とギャンブルに明確な境界線はない,と.
いや,それでもできてない😅
南海トラフ地震は向こう30年以内に70〜80%,首都直下地震は同じく70%.
金融証券会社にしてみれば,リスクを過小評価しても最後は「自己責任」で逃げられます
期待値は1未満.
最高裁判事にも常識があったというところが画期的かもしれません😅
合法的に利益を上げ続けていく上で外れ馬券を経費と認めたこの最高裁判決は重要です.
もちろん莫大な時間とカネをかけてシステムを完成できればの話で,自分でやるつもりは毛頭ないです😅
場合によっては長期的にも.