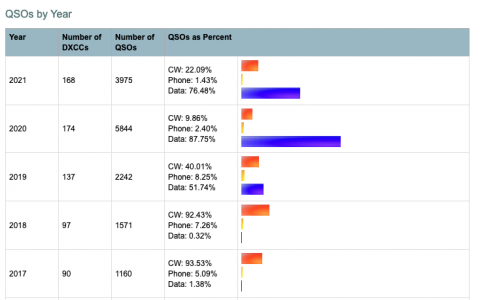Macbookの方は特に問題なくMontereyで稼働し続けています.余勢を駆ってメインWSであるところのMac miniもMontereyにupgradeしました.Catalinaで動いている状態にupgradeをかけた形です.もちろんですが,upgrade前に外付けのSSDにクローニングしました.
upgrade後,機能拡張がいくつもはじかれて,Wacomのタブレットが使えません. “システム環境設定”のセキュリティーとプライバシー→プライパシーと開くと,「Wacomの機能拡張が読み込めません.再度読み込みますか」という趣旨のダイアログが出て,ボタンは「OK」しかないので,OKを押すとその何秒か後にまた同じダイアログが出ます.どうしようもないので,電源リセットして,システム環境設定を開かなければよさそうだと気付いて,システム環境設定に触れずにいくつかアプリを起動しました.
しかし,肝心なWSJT-Xが無線機と通信してくれません.
ls -l /dev/cu.*
を実行すると,FTDIのUSB-serialポートがひとつも表示されません.何回かMac miniを再起動をしていると,FTDIを含む多数の拡張機能が信頼できないから読み込めないというダイアログが出ました.
FTDIから最新のドライバーをダウンロードすることも考えましたが,また「Wacom…」が出始めると,電源リセットすることになるので,今回メインWSであるMac miniをMontereyにupgradeすること自体断念しました.
バックアップしておいた外付けSSDから起動してさくさくっと復旧,のつもりが,ここからが半日仕事になりました.
Catalinaの外付けSSDからの起動も紆余曲折がありましたが,最終的にはなんとかできました(たしか起動時にOptionキーを押しても起動ドライブ選択メニューが出ないので,MontereyからWacom嵐をなんとか切り抜けて,システム環境設定で起動ドライブを設定して起動したのだと思います)が,ディスクユーティリティーで内蔵SSDを初期化してもCarbon Copy Cloner (CCC)がコピー先が不適切だと,仕事を拒否します.CCC のV5も,有料upgradeしたばかりのV6も同じです.
仕方がないので,Catalinaのインストーラーをダウンロードして,初期化した内蔵SSDにインストールを試みたところ,うまくインストールが始まりました.
復元の選択で外付けのSSDを選んで何時間か後にようやく,ほぼCatalinaで動いていたときの最終状態に近づきました.
ここでもう一度外付けSSDから起動して,CCCで外から内へのクローニングを実行して,Montereyへのupgrade直前の状態に戻りました.
今後ですが,FTDIのドライバーがMonterey対応になっているか調べて,そうならそのドライバーを準備します.また,次回のupgradeは内蔵ドライブに対して行わず,外付けのSSDに行うことにします.復元作業に時間がかかりすぎるので.
追記: FTDIのドライバーはやる気なさそう
タイトルの通りですが,FTDIのVCP Driverのページを見たところ,MacOS 11 (Big Sur)対応がβ版だそうです.Monterey (MacOS 12)でも使えるかも知れませんが,あえて火中のクリを拾うようなことになりそうですね.
ということで,やめときます.
追記の追記: インストールはできた
とりあえず,FTDIのUSB-serialアダプターなどと言う時代遅れのディバイスをつなぐことのないMacbookに,FTDI VCP driver 2.4.4 (macOS Catalina対応)のインストールを試みました.インストーラーは正常終了しましたが,OSが不適合な機能拡張だとはじきました.
次にBig Sur対応のβ版を試したところ,インストールができて,OSも,「システム環境設定」のセキュリティーとプライバシーで,受け入れればOKとなりました.
動くかどうかは解りません.