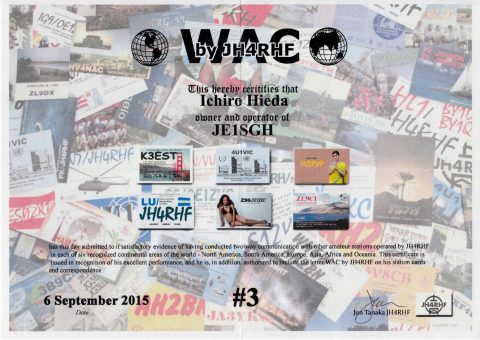一週間くらい前に,自宅の4エレクワッドアンテナの端のエレメントが両方とも取れてしまった夢を見ました^^;
実はタワーの周辺の立木が茂ってしまい,この10年くらい両端のエレメントについては点検できていないのです.普通に降ろすとここまでが限界です.

これだと,ブームの地上高はまだ8m強あり,両端のエレメントの取り付け部分の点検はできません.ということで,長いこと両端エレメントについては点検できていないのです.正夢になっては困るので点検することにしました.
どのように点検するか,いろいろ考えてみました.上からロープでぶら下がってブームを伝わって端まで行く.まあ,これは机上の空論どころか,漫画ですね^^;
次に考えたのは,はしごタワーです.8〜10mクラスのはしごを買ってきて,しっかりステーを付けて立たせる.これは実現性はありそうですが,かなりの大仕事になりそうです.しっかりしたステーが取れず,倒れでもしたら命に関わります.
最後に思いついたのは高枝切りばさみで,エレメントが引っかかりそうな枝を切るという方法です.高枝切りばさみを使ったことはないのですが,費用もそれほどではなく,転落などの心配がないので安全性も高く,現実的な方法なので,この方法にすることにしました.
ちょうど今日はもろもろ都合が良いので休暇を取ってアンテナ点検を実施することにしました.
これまで高枝切りばさみは使ったことがないので,どういうものがいいのか,見当はつきませんでしたが,竿の長さが4mで,なるべく太い枝が打てて,ノコギリも付けられる,あたりかなと想定しました.
近所のホームセンターに行ったら,手頃なのがありませんでした.そこで,有名なジョイフル本田(のたぶん本店)に行ってみました.
 平日だというのに駐車場は大混雑でした.さいわい店内はすいていました.久しぶりに来たので,見当が付かないので,店員さんに聞いて高枝切りばさみの売り場までたどり着きました.
平日だというのに駐車場は大混雑でした.さいわい店内はすいていました.久しぶりに来たので,見当が付かないので,店員さんに聞いて高枝切りばさみの売り場までたどり着きました.
さすがに品揃えが多くあり,4m,25mmの枝まで打てて,ノコギリも付けられる(付属)というのがありました.アマゾンより1,000円高いのですが,今使いたいので仕方ありません.
実際に枝をうちながらアンテナを少しずつ降ろしました.20〜25mmくらいの太さの枝は上の方にもいくらでもあり,12mm, 15mmまでという半端な品を買わないで正解でした.もっと太い枝も2回ほど打つ必要があり,ノコギリも役に立ちました.ノコギリはコツが要りますね.
ここまで降ろしたのは,たぶん,4エレにして,上げて以来13年ぶりではないかと思います.

ここまで降ろすと,脚立に乗って両端のエレメントの取り付け部分の点検ができます.

ブームへの取り付けのボルトや,スプレッダーの取り付けねじの増し締めをしてみました.ブーム取り付けのボルトはほとんど回らないほどよく締まっていました.
ついでに給電部分のテーピングのやり直し,アンテナトラックとワイヤーの接合部分の点検などもしました.
非常に良い作りなので安心しました.
追記
スプレッダー部分は,樹脂部分の劣化があるので,増し締めしない方が良かったと思います.寿命を縮めてしまったと思います.