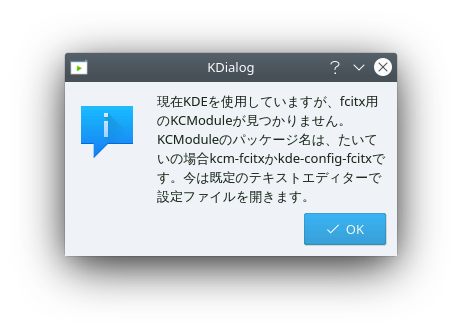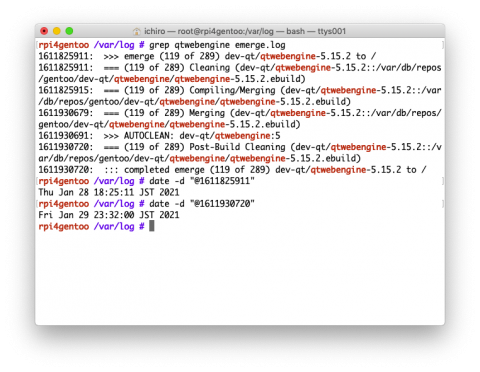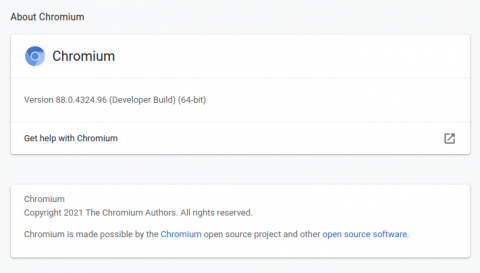仮想マシンのほうがなかなからちがあきません.まともに動くのがありません.
Linux + QEMU/libvirt/Virt-Manger
仮想マシン自体の動作には全く問題がありませんが,Virt-mangerのバグのため,スナップショットのマネージメントができません.
macOS + VMWare Fusion
画面の解像度が800×600でしか動きません.
macOS + VirtualBox
CPUの温度が上がったり,全く原因不明だったりしますが,segmentation fault (segfault)が頻発して,使い物になりません.
そこで考えたのですが,macOSでQEMU,libvirt,Virt-Mangerをインストールできないかということです.利用しているMacPortsには,一通りそろっています.
QEMUとlibvirtは問題なくintallできましたが,Virt-mangerはNGです.バグのようです.
virt-manager @2.2.1_3+x11 Configure error – build failure: “gtksourceview4 must be installed with +x11 and without +quartz”
このバグか解消されるのを気長に待ちましょう.