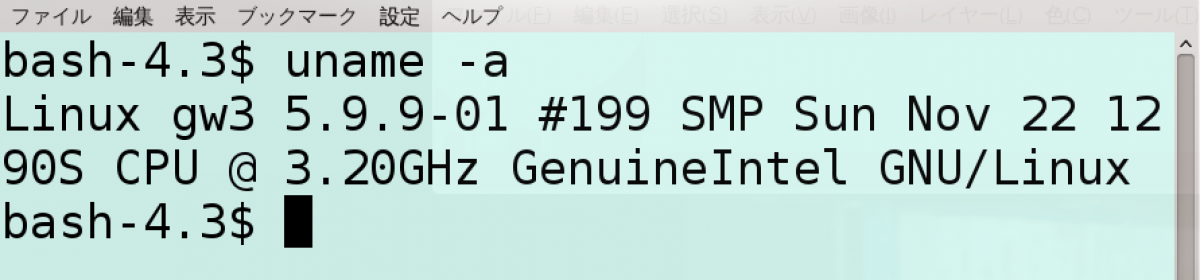今朝,ジムバトルから帰ってくるとわが家の植え込みにアシナガバチが入り込む様子を見ました.この植え込みにはアシナガバチがよく巣を作ります.
アシナガバチはおとなしいのですが,それでも蜂です.以前植え込みを刈っていたら,営巣中の女王蜂に左手の親指と人差指の股の部分を軍手の上から刺されてずいぶん腫れたことがあります.刺されてから気がついたのですが,巣の数十センチ手前あたりを無造作に刈り込もうとしていて,女王蜂は巣を壊されまいと必死の抵抗をしたのでしょう.蜂だなと感心したのはすっと飛んできてさっと刺して去っていきました.一瞬でした.蚊が刺すのと全然違います.
気の毒ですが,巣に戻った女王蜂にたっぷり殺虫剤をかけて殺しました😓 ちなみにアシナガバチはキンチョールで十分効果があります.
以来植え込みにアシナガバチが出入りしているところを見つけると殺虫剤を持ってきますが,ほんの何十秒ですが戻った頃にはそこには大抵いません😓
今朝は,見つけた場所ではないですが付近をまだホバリングしていたのでアースジェットをかけました.
アースジェットはキンチョールよりたいてい安く売っていますが,すぐに中身が空になるのであまり得ではありません.しかし今朝は家人がキンチョールを墓参りに持っていくよう荷造りしてしまったので,やむなく残り少ないアースジェットを使用したわけです.
ホバリングしているところにスプレーしましたが,アースジェットがちょうど切れた事もあって十分に当たった手応え😓がありません.
この後アシナガバチはお隣の二階のひさしまで急上昇し,すぐに下降してわが家の別の植え込みの周辺を飛行し,また2階屋の屋根くらいまで急上昇してから急下降して,なんとアースジェットを持っている右手にぶつかりました.
慌てて振り払いました.刺されはしませんでしたがこの後のアシナガバチの行方は追えませんでした.多分殺虫剤は十分かかっていて死ぬ前の異常行動をしたのだと思いますが,アシナガバチの最後の執念というか怨念を見たような気がします.